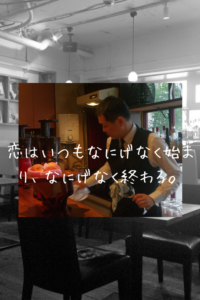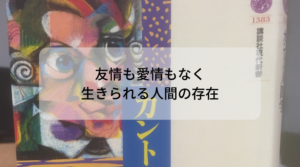【読書感想】『知的生活の方法』を読むと、自分の知識を蓄えられる
最近は早寝早起きなやっちです。
「知的生活の方法」という本を読みました。
本を読んだ気になって、わかったフリをして、「知的生活の方法」を読んだよ! と言うのだけはやめようと思えた本でした。
結論から言いますと、1回読んだだけではわかりませんね、これは。
著書の中でも頻繁に言われている、繰り返し読む「精読」をしないことには、半分も理解できません。
理解できないというのは難しい内容なのかというとそうでもなく、スラスラと読みやすくはなっているのです。
僕は読書が好きなので、読書という点で印象に残った点に触れていきます。
本は、繰り返し読むことで「わかった」になる
著者の友人が、ある本について「これは読んだことがあるような」と悩んでいたシーンが印象的でした。
なぜ私がそんなに驚いたかと言うと、
一度読んだかどうかよくわからない『少年倶楽部』を、
ひょっとしたら読んだことがあるかも知れないという怖れから、
すぐ借りないということが、どうしても不可解だったからである。
この本、読んだことがあるような。
この映画、前に観たことがあるような。
そんな迷いから、手に取ることをやめてしまったことってないでしょうか。
一度読んだことがあるかどうかの記憶も確かでないのに、
借りるのを躊躇しているのだ。
一度読んだ本を読みかえすのはそんなに損することなのだろうか。
損するかというものさしで考えてみれば、買ったものをもう一度買うという点において損することもあるかもしれません。
しかし、今の自分にとって再び必要になった本だとしたら、知識を自分のものとするために改めて買うのは、果たして損なのでしょうか。
そんな風に考えさせられました。
文体の質とか、文章に現れたものの背後にある理念のようなものを感じ取れるようになるには、
どうしても再読・三読・四読・五読・六読しなければならないと思う。
何かを感じとるためには反覆によるセンスの練磨しかないらしいのである。
読んで何かを得る、ということはしてきたのですが、「感じとる」についてはとても浅かったように思えてならないのです。
僕は、再読まではよくしていますが、六読まではいきません。
さらには、繰り返し読めばいいものでもないということがよくわかります。
感じとる領域にたどり着けるならば、一読で終わりにしてもいいと思うのです。
多忙な主婦の知的生活
たくさんの本を繰り返し読んでいくことが知的生活につながるかというとそうでもないと思ったのが、この部分でした。
私の親類に、短歌の好きな老夫婦がいる。
だいたい女性というのは、学生でもなかなか余分の本は買わないものだが、
一家の財政を預かる主婦ともなればなおさらである。
ところがこの主婦の書棚には、本がわずかながらも確実に増えているのである。
その増え方は、今の私が一ヶ月で買う分量が十年近くもかかって増えるといった程度のゆるやかなものだ。
しかし増えている本はちゃんとした本である。
多忙な主婦でも、確実に知的生活をしていることはこれを見ただけでも確かである。
僕は、自分が買う本は今の自分を表していると思っています。
なので、日々変わっていって当然です。
何年も本棚の本が変わらない人というのは、僕がそうであったように、現実もあまり変わっていないんですよね。
著者が言うには、「日常生活のみをやって過ごした」ということで知的生活はなかったということになります。
長年の蓄積があれば、本は2ヶ月で書ける
日々、得た情報を整理していますか?
書いてあったことを思い出そうとしたときに、どこにしまっておいたか思い出せますか?
脳の中に留めておくことはなかなか難しいので、メモアプリのEvernoteを使ったり、手帳に書いたり、ブログに残したりしますよね。
著者は専門家ではないもののドイツ参謀本部についての本を書くことになった際に、このように言っています。
いざ書き始めてからからは、平均して一章に二週間ぐらいの時間をかけ、五章を約十週間で書き上げた。
この本を書くために使った日数は正味で二ヶ月ぐらいである。
これはすべて、長年かけて関係文献を並べておくだけの空間があったことによる。
空間さえあれば、心がけしだいで、素人でも専門家に見てもらえる本が書けるという一例である。
資料を多く持ち、そして整理されていたんですね。
何がどこにあるかを知っているということは、大きな武器になります。
読書のあと、関連した内容のものについてはグループ分けし、「関連書籍はここにある」という場所が常にわかっている状態が「自分に蓄積した」ということなのだと思います。
本書では食事、散歩、家族についてなどの身近なことについても触れられています。
あくまで生活の質を高めるためには何ができるだろうか? ということを探求した内容となっています。
少しでも楽しい生活を送りたいと思う人には、価値がある本になりそうです。